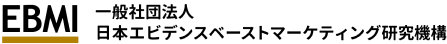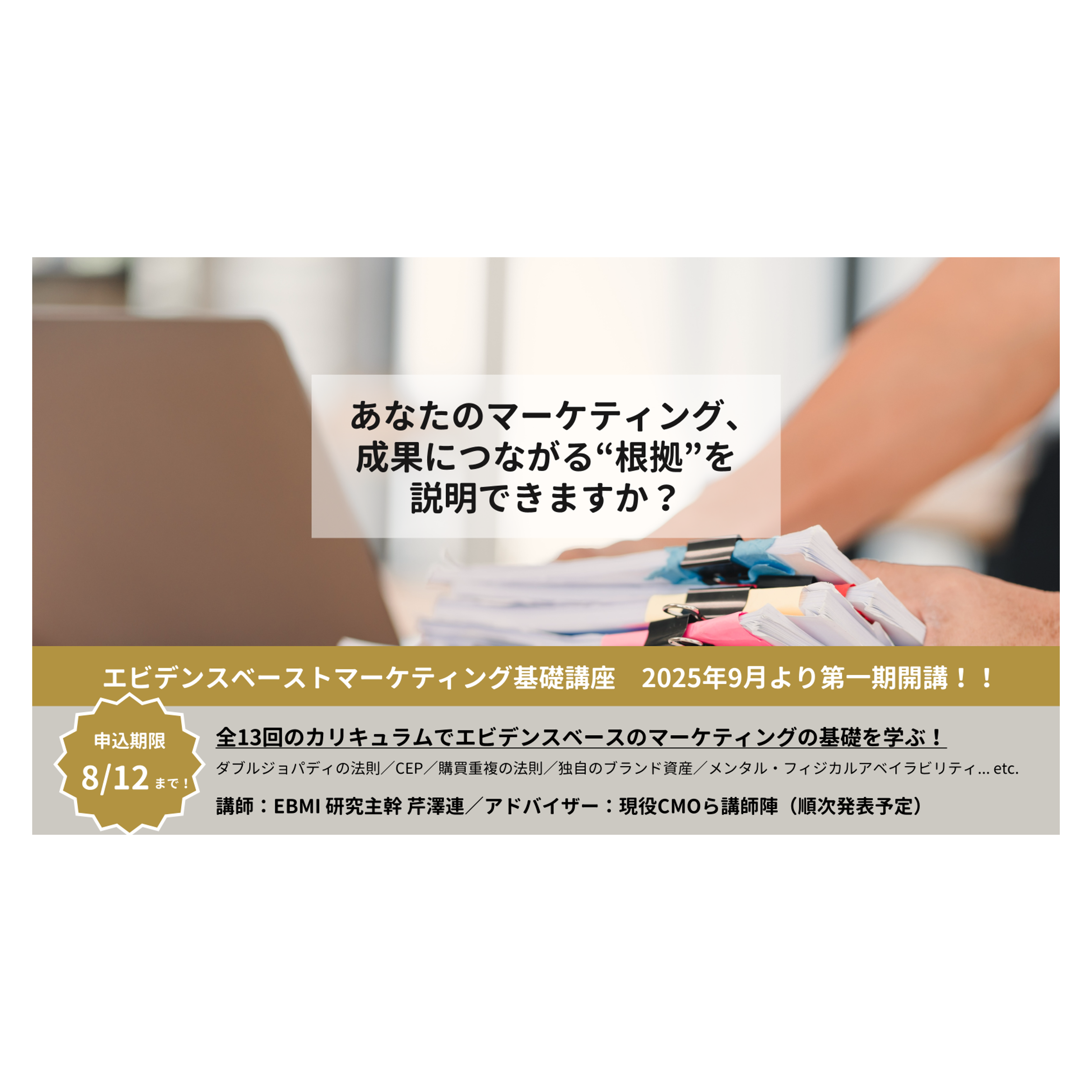研究分科会設立・運営ガイドライン
はじめに
本ガイドラインは、一般社団法人日本エビデンスベーストマーケティング研究機構(以下「EBMI」という)における「研究分科会」(以下「分科会」という)の設立・運営に関する基本的な手順を示すものです。ここに示す内容は、EBMI参加規則(以下「会則」)およびEBMI公式サイトに掲載されている「分科会の設立、運営規定」を踏まえています。
個別のケースで本ガイドラインと会則や公式サイトの記載に相違が生じた場合は、そちらが優先されますのでご留意ください。
1.分科会設立の目的と意義
- 共同研究による課題解決
分科会は、企業単独では解決の難しいマーケティング上の課題に対して、EBMIに加盟する複数企業や専門家が協働する場です。原則として無償かつ共同的な研究を通じ、会員企業ならびに公共性のある成果を生み出すことを重視しています。 - エビデンスベーストマーケティングの推進
分科会で得られた成果は、実務に役立つ形で広く公開・共有されることが基本方針です。適切なデータ分析・検証を行うことで、研究成果の再現性と有効性を高め、マーケティング全般の知見向上を目指します。 - 人材育成とネットワーク形成
分科会の活動を通じて、参加する委員は最先端のマーケティング理論や手法を学び、他社のマーケターや研究者とのネットワークを構築できます。企業の成長のみならず、業界全体のマーケティング力向上につながります。
2.設立要件と手続き
【2.1 評議員による設立】
分科会の設立は「研究振興評議会の評議員のみ可能」とされています。これは、エビデンスベーストマーケティングの実務的要請を出発点とするためです。具体的には、1名以上の評議員が以下の事項をまとめた研究計画書を研究振興評議会へ提出し、審査を受ける必要があります。
- テーマ
- 背景・ゴール
- リサーチクエスチョン
- 参加する委員の構成(企業・担当者 など)
研究振興評議会と研究主幹による審査で承認が得られた時点で、正式に分科会が立ち上がります。
【2.2 委員長・委員の選定とパートナー活用】
<委員長と委員>
分科会は、委員長と委員によって構成されます。
- 委員長
研究振興評議会に属する評議員が就任し、研究分科会全体の運営責任者として進捗管理や成果発表を担います。 - 委員
研究分科会活動を担うメンバーであり、委員長が指名した社内公募の社員やパートナー企業の研究者などが該当します。必要に応じて、副委員長に任命し、分科会の運営や研究の指揮を委任できます。
<社内公募の実施>
評議員は所属企業の社員を招へいし、当該社員に分科会の設立・運営業務を担わせることができます。 その際、大きく2つのパターンが想定されます。
- 立ち上げ前の公募
- 分科会が正式に発足する前に、評議員が自社内で公募を実施
- 集まった社員とともに研究テーマや計画をまとめ、評議員が委員長となり分科会を立ち上げる
- 立ち上げ後の公募
- すでに分科会が発足している状態で追加の公募を行い、評議員が在籍する企業の社員を新規に委員として迎え入れる
- より多くの社内メンバーを取り込み、研究や運営業務を担わせることで分科会の活動を強化する
いずれのパターンでも、最終責任は評議員(委員長)が負うことになり、社内公募の対象範囲は評議員が所属する企業内に限られます。
<パートナー企業の活用>
分科会をより充実させるため、委員長は独自のパートナー企業を巻き込み、研究に必要な専門知識やリソースを補うことが可能です。パートナー企業から指名される研究者は、分科会の委員として参加できます。
【2.3 研究計画書の要件と例】
研究計画書には、次の内容を明確に記載してください。
- テーマ:分科会で取り組む具体的な領域
- 背景・ゴール:研究に取り組む理由や現状の課題、最終的に目指す成果や指針
- リサーチクエスチョン:研究で明確化したい問い、検証したい仮説
- 参加する委員の構成:委員長、副委員長、委員の氏名や役職を明記
他分科会の例:デジタルアベイラビリティ研究分科会
- テーマ
デジタルマーケティングの次世代戦略を探求し、エビデンスベースな手法を駆使して新たな知見を提供する - 背景・ゴール
- 消費者の需要発生(CEP)から購買までのプロセスを理解し、デジタルタッチポイント(検索連動広告、SNS広告、オウンドメディア等)の価値を明確化する
- LTV(顧客生涯価値)の高いCEPを発見する手法を確立し、デジタル媒体選定の具体論を導き出す
- リサーチクエスチョン例
- LTVの高いCEPをどのように見つけ出すか?
- 特定の検索ワードやコンテンツが購買・離反に与える影響とは?
- デジタルメディアの効果や効率、適切な組み合わせはどう見極めるのか?
- 分科会メンバー
- 委員長:〇〇 〇〇(評議員)
- 副委員長:〇〇 〇〇
- 委員:〇〇 〇〇
- 委員:〇〇 〇〇
- 委員:〇〇 〇〇
- 委員:〇〇 〇〇
以上のように、研究計画書では研究の全体像が把握できる情報を簡潔にまとめ、研究振興評議会へ提出してください。審査の詳細プロセスや評価基準は、EBMI会則および研究振興評議会の指示に従ってください。
3.分科会の運営ルール
【3.1 活動計画と会議】
分科会発足後、承認された研究計画書を指針として定例会議を実施します。進捗報告・課題の共有・データ分析のレビューなどを行い、必要に応じて計画を修正することも可能です。会議の頻度は各分科会の判断に任せられますが、EBMIから定期的に進捗報告の要請があるため、それに応えられる形で会議を行うことが望ましいです。
【3.2 研究テーマの公共性】
分科会で扱う研究テーマは、会員企業や公共にも利益をもたらす内容が原則です。たとえばカテゴリー市場の分析など、多くの企業に有用な知見が得られる研究を推奨します。一方、特定企業のブランド戦略のみを対象とするような閉鎖的な研究は分科会の趣旨に合致しないため認められません。
【3.3 成果報告の義務】
各分科会は年に1回以上、研究成果を研究振興評議会および研究主幹へ報告し、レビューを受ける必要があります。通常は年次の定期イベントや報告会の場を活用しますが、詳細はEBMI事務局の案内に従ってください。
【3.4 進捗管理と紛争解決】
委員長や副委員長は、研究進捗やタスク状況を定期的に把握し、課題が発生した場合は委員間で速やかに共有・協議します。分科会活動に関するトラブルや紛争が生じた場合は、当事者間での解決が基本です。
4.成果の公開と機密保持
【4.1 原則としての情報公開】
EBMIの研究分科会は、競合企業であっても見られて困らない範囲の成果を、できるだけ広く公開し、マーケティング知識を社会に還元していくことを基本方針としています。EBMIはレビュー会や発表会の参加者から特定企業(競合など)を排除することは基本的に行いません。
【4.2 公開レベルの設定】
研究に用いるデータやノウハウには機密性が高い場合もあります。会則(特に第12条等)に定めるとおり、データ提供者や委員は公開範囲を調整できる権利を有します。たとえば以下のような運用が考えられます。
- 分科会内の限られた委員だけに共有する(厳格な機密扱い)
- EBMI内で評議員・会員等には公開するが、一般公開はしない
EBMIとしては「公共性のある研究成果を広く届ける」ことを重視するため、過度に非公開設定を行うことは推奨しません。研究テーマやデータ提供者と協議し、バランスを取った公開レベルを設定してください。
【4.3 秘密情報の取り扱い】
分科会活動において知り得た機密情報は、会則の秘密保持規定(第4条など)に準拠して扱う必要があります。委員が退会・除名・解任された場合でも、秘密保持義務は存続しますので、取り扱いには十分にご注意ください。
5.費用負担と報酬の扱い
【5.1 活動費用の原則】
研究活動費やリソースは、各分科会が持ち出しで行うことが基本となります。調査費用や分析ツール利用料なども参加企業が自己負担し、分科会内で費用負担を調整してください。
【5.2 報酬に関する取扱い】
分科会の委員やパートナー企業に対する金銭的報酬は原則発生しません。あくまで企業や公共の利益に資する研究を共同で行う場であるため、会則上も無償活動が前提となります。ただし、EBMI本体から執筆や講演を個別に依頼される場合などは、別途謝礼が発生する可能性があります。
6.EBMI本体との連携・報告
【6.1 定期報告】
前述のとおり、分科会は年に1回以上、研究成果および進捗について研究振興評議会へ報告する義務があります。通常は年次の定期イベントや報告会の機会を活用しますが、会則や事務局の案内に応じて運用してください。
【6.2 中間報告・サポート】
長期プロジェクトや大規模研究の場合、中間報告を行いながらEBMI事務局や研究主幹と連携を取り、必要に応じて助言や調整支援を受けることができます。会則上、EBMIは研究活動そのものに干渉しない立場を取っていますが、分科会の円滑な運営をサポートするため、適宜ご相談ください。
7.トラブル・違反時の措置
【7.1 トラブル時の基本方針】
分科会活動中のトラブルや紛争は、当事者間の協議・解決が基本です。データ利用や公開範囲に関する意見相違、費用分担の問題などが生じた際は、まず分科会内で話し合い、合意形成を図ってください。
【7.2 違反時の対応】
会則に反する行為(情報漏えい、名誉毀損等)があった場合、会則に定める手続きに基づき、除名や参加停止などの措置がとられる可能性があります。免責事項や損害賠償請求に関する規定については、詳細を会則にてご確認ください。
8.その他
【8.1 委員の交代・退会等】
研究途中での人員変更が生じた場合は、委員長とEBMI事務局に連絡のうえ、円滑な後任移行を目指してください。
【8.2 ブランド個別戦略の取り扱い】
分科会の趣旨は、広く会員企業や公共に利益をもたらす研究であり、特定企業が自社ブランドの戦略策定のみを目的とする場合は分科会の対象外です。そうした個別案件は、各企業が独自に行うか、別の形態で進めることを検討してください。
【8.3 ガイドラインと会則・規定の関係】
本ガイドラインは、分科会設立・運営の流れを分かりやすく示すためのものであり、法的拘束力や優先度は会則および公式サイトの規定に劣後します。各分科会は会則・規定を十分にご確認のうえ、必要に応じて事務局と連携しながら活動を進めてください。
終わりに
EBMI研究分科会は、企業の枠を超えた共同研究を通じて、日本のマーケティングをエビデンスベースで進化させるための重要な取り組みです。本ガイドラインを参考に、適切な委員長・委員構成と研究計画書の策定を行い、分科会活動を円滑に推進いただければ幸いです。疑問点や運営上の課題が生じた際は、EBMI事務局へお気軽にご相談ください。
※本ガイドラインは、EBMI会則および「分科会の設立、運営規定」の要点を踏まえて再構成したものです。詳細事項や追加規定については、会則・公式サイトの該当部分を参照のうえ運用してください。