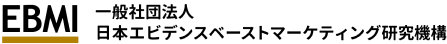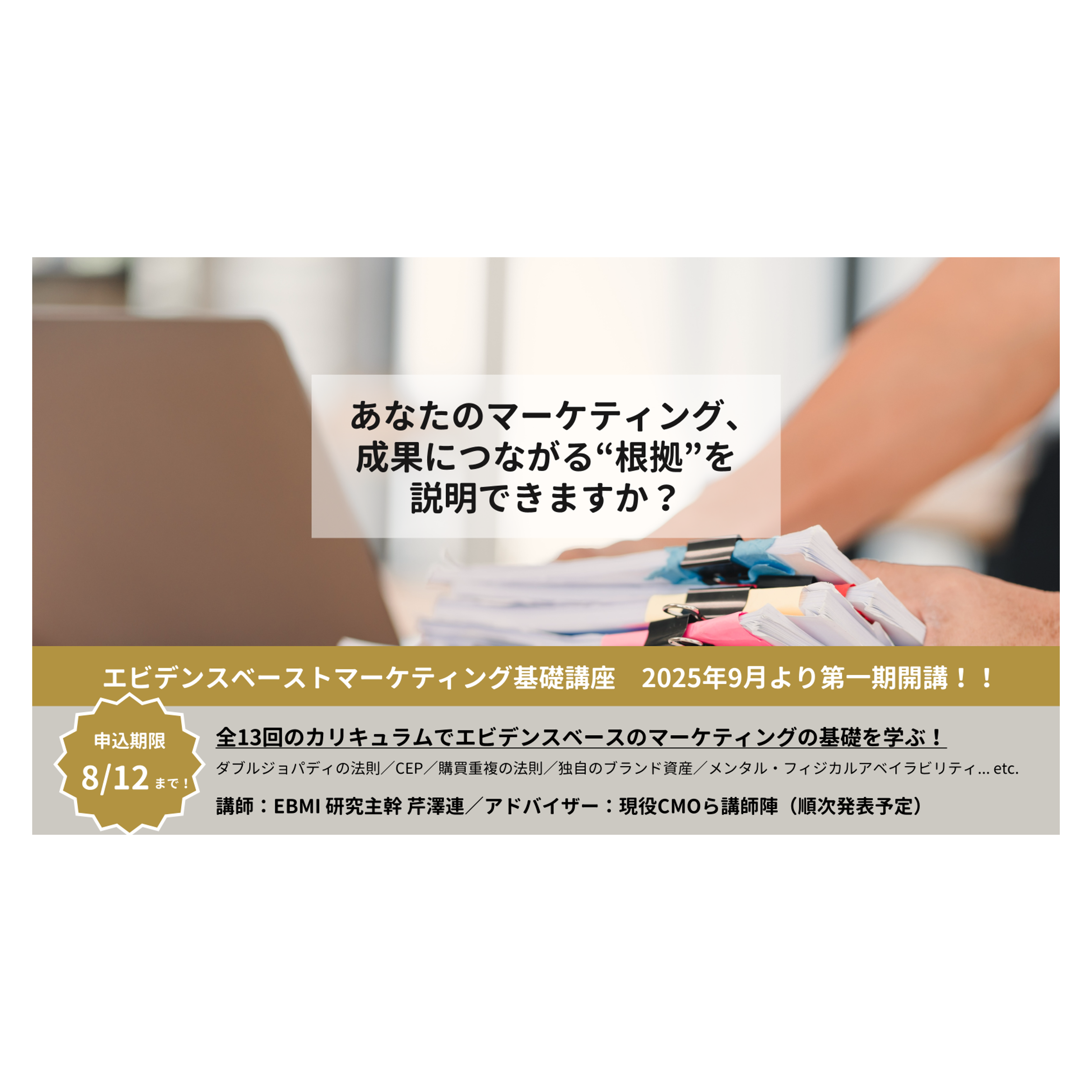参加規則
第1章:総則
第1条(本資料について)
本資料は、一般社団法人日本エビデンスベーストマーケティング研究機構規則(以下、本規則とする)とし、一般社団法人日本エビデンスベーストマーケティング研究機構(以下、本機構とする)参加者の参加規則を定めるものである。
第2条(目的)
本機構は、日本におけるエビデンスベーストマーケティングの研究、啓蒙および実践の支援を目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
- エビデンスベーストマーケティングの日本における実証研究、および研究成果の発信や研究データやレポートの販売
- エビデンスベーストマーケティングの教育プログラムや教材の提供
- エビデンスベーストマーケティングの実践を希望する法人や個人の紹介や斡旋
- その他、本機構の目的を達成するために必要な事業
第3条(参加者)
本機構の参加者とは、「研究振興評議会」、「研究分科会(研究パートナー企業を含む)」 、「アカデミックアドバイザー」、「スペシャリスト」および「会員社」としての参加を指す。
第4条(秘密情報)
- 本規則において「秘密情報」とは、一般社団法人日本エビデンスベーストマーケティング研究機構(以下「本機構」という)または本規則の参加者(評議員、アカデミックアドバイザー、スペシャリスト、会員社、研究分科会参加者、研究パートナー企業その他、本機構が認める者を含む。以下同じ)が開示または提供する一切の情報(文書、図面、電子データ、口頭、その他いかなる形式によるかを問わない)及び、開示時に秘密または部外秘である旨が明示されたもの、またはその性質上秘密であると認められるものをいう。
- 秘密情報には、研究データ、マーケティング戦略、顧客情報、技術情報、ノウハウ、財務情報、ID・パスワードその他のセキュリティ情報、本機構が部外秘として提供する会員向け教材・動画・資料・ナレッジベース等を含むものとする。
- ただし、次の各号に該当する情報は、本条が定める秘密情報に該当しない。
- 開示を受けた時点ですでに公知であった情報、または開示後に受領者の責めによらず公知となった情報。
- 受領者が正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報。
- 受領者が開示を受ける以前から保有していたことを証明できる情報。
- 本機構または情報提供者が秘密保持義務を課さずに開示・利用することを書面等により許諾した情報。
- 開示を受けた時点ですでに公知であった情報、または開示後に受領者の責めによらず公知となった情報。
第5条(秘密保持義務)
- 本機構の参加者は、前条で定義される秘密情報を厳重に管理し、本機構の目的(エビデンスベーストマーケティングの研究および実践の支援)を達成するために必要な範囲を超えて利用し、または第三者に開示・漏洩してはならない。
- 本機構の参加者は、在籍中のみならず、退会・除名・解任その他の理由により参加資格を喪失した後も、秘密情報を第三者に開示、漏洩、または不正に使用してはならない。
- 本機構の参加者が、自らの業務や研究活動上やむを得ず従業員、協力会社、関係会社等の内部関係者に秘密情報を開示する場合、当該内部関係者にも本条項と同等の秘密保持義務を遵守させる責任を負う。
- 本機構の参加者は、秘密情報の漏洩、不正使用、またはそのおそれがある事態を発見した場合、速やかに本機構へ報告するとともに、被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとする。
- 本機構の参加者が本条項に違反した場合、本機構は第32条(違反時の措置および損害賠償)その他関連規定に基づき、除名・参加停止や損害賠償請求などの必要な措置を取ることができる。
第2章:研究振興評議会に関する規則
第6条(研究振興評議会の参加者)
研究振興評議会の参加者は「評議員」と呼称し、本機構の総会(または理事会)が発行する委嘱状で任命されることで参加できる。また、評議員は原則として自社が有するサービスやブランドに関するマーケティング活動全体を監督する立場にある役職者(例:CMO等)が任命される。
第7条(評議員の業務)
任期中の評議員は、原則として以下の事項に取り組むものとする。
- 本機構の研究成果についてのエビデンスレベル評定会議(年4回)への原則参加
- 研究報告会(随時)・大会(年1回予定)への原則参加
- ウェブサイトへの顔写真、氏名、所属、役職の掲載
- 所属企業社名およびロゴ画像の本機構ウェブサイト、各種資料への掲載に係る手続きの実行
- 評議員、アドバイザリーボード、協賛企業等への本機構紹介および勧誘
- その他、本機構の広報支援や、エビデンスベーストマーケティングの振興に係る業務
第8条(評議員の情報アクセス)
任期中の評議員は、以下の規則に基づき本機構の情報を扱う。
本機構の研究成果に関する資料やデータは(総則第4条で定める)秘密情報にあたるため、部外秘(※1)として扱う。委嘱中、または委嘱終了後も、秘密情報の不正な持ち出し(撮影、スクリーンショット取得、コピーを含む)、開示、不正使用は行わない。
※1:本機構内の情報は「研究分科会内でのみ公開」「評議員のみに公開」「評議員、分科会、協賛企業のみに公開」「一般公開」等のレベルにより管理される。管理レベルに沿った情報の管理に努める。
第9条(評議員の報酬)
評議員就任についての報酬は発生しない。ただし、執筆や登壇など、本機構が定める依頼を受けることで発生する報酬は、個別の取り決めに基づいて支払われるものとする。
第3章:研究分科会に関する規則
第10条(研究分科会の組織と目的)
研究分科会は、総会(または理事会)が定める研究統括と、研究テーマごとに1名以上の評議員および1社以上の研究パートナー企業が参加する各分科会により構成され、本機構の目的であるエビデンスベーストマーケティングの各種研究活動を行う。
第11条(評議員による社内公募と分科会運営)
評議員は、以下の規定に基づき、所属企業の社員を招へいし、当該社員に分科会設立・運営業務を担わせることができる。
- 社内公募により選出された社員も、本規則第16条等で定める研究データや成果物の取扱い、秘密保持義務、報酬規定に準じて活動する。
- 当該社員が分科会の実務を主導する場合も、研究分科会の最終的な責任は評議員が負うものとする。
- その他詳細な運営方法や権限範囲については、研究パートナー企業および分科会メンバーとの協議を経て定める。
第12条(研究分科会の設立)
研究分科会を設立する場合は、評議員が発起人となり、研究パートナー企業と共に研究計画書を作成し、総会(または理事会)の承認を経ることで設立される。
第13条(研究分科会の業務)
研究分科会は、原則として以下の事項に取り組むものとする。
- 研究計画に基づいた研究活動の実施
- 分科会の研究成果について年1回以上の発表
- 大会(年1回予定)への参加
第14条(研究分科会の報酬)
研究分科会に参加する研究統括、評議員および研究パートナー企業への報酬は発生しない。
第15条(研究パートナー企業へのID発行)
- 研究パートナー企業には、会員社(レギュラー会員)と同等の会員向けコンテンツを閲覧するためのIDを1社あたり3IDを上限として発行する。発行されたIDの利用に際しては、第29条(会員IDの利用規則)を遵守するものとする。
- 前項に定めるIDの発行は、次の各号に掲げるすべての条件を満たすことを要する。
- 当該研究パートナー企業が参加する研究分科会において、第13条に定める業務を誠実に遂行すること。
- 本機構からの要請に基づき、会場の提供をはじめとする、本機構が主催するイベントその他の活動への協力を行うこと。
- 本機構の活動に資するデータ、分析結果又は報告資料(以下、本号において「データ等」という。)を年間を通して継続的に提供し、本機構がこれを利用できるようにすること。この提供には、次に掲げる事項を含むものとする。
- 所属する研究分科会の研究計画に基づき実施した研究の成果
- 本機構の会員社及び評議員向けの勉強会又は学習コンテンツに利用するためのデータ等
- 本機構が行う広報活動(外部メディア向けの記事作成、イベント登壇、出版その他のPR活動を含む)に利用するためのデータ等
- 正当な理由なく前項の業務が遂行されていないと判断される場合、総会(または理事会)の決議により、当該研究パートナー企業のID発行および利用を一時的に停止することができる。
- IDの発行および利用を停止された研究パートナー企業が、その後、業務の遂行を再開し、その状況に改善が認められた場合、総会(または理事会)の承認を経て、IDの発行および利用を再開することができる。
第16条(研究データや成果の取扱い)
研究分科会で扱われるデータや研究成果については、以下の定めに基づき扱うものとする。
- データや情報の提供・二次加工の取扱い
研究に用いるデータや情報を分科会メンバーが提供する場合、当該データや情報に関する一切の権利は提供者に留保される。また、提供されたデータや情報を基に作成された二次的著作物(加工データや派生研究成果を含む)についても、その権利帰属や使用範囲は提供者との合意に従うものとする。
いずれの場合も、分科会内で行われている研究内容やデータを、当該分科会の部外者が提供者の許可なく閲覧・使用することはできない。 - 研究成果の公開前における範囲設定
研究分科会の研究成果を評議員への報告会や対外的な場で発表・公開する前に、公開する研究成果および関連データの公開範囲や取扱いについては、データ提供者が個別に定めることができる。 - 本機構への成果活用
研究分科会の研究成果は、本機構の会員向け学習コンテンツや対外メディア記事などに利用される。
第4章:アカデミックアドバイザー、スペシャリストに関する規則
第17条(アカデミックアドバイザー)
「アカデミックアドバイザー」は、本機構の総会(または理事会)が発行する委嘱状で任命されることにより参加できる。また、アカデミックアドバイザーは、原則として大学などの研究機関に所属する研究者が任命される。
第18条(アカデミックアドバイザーの業務)
任期中のアカデミックアドバイザーは、原則として以下の事項に取り組むものとする。
- 本機構の研究成果についてのエビデンスレベル評定会議(年1回)への原則参加
- 研究報告会(随時)・大会(年1回予定)への原則参加
- ウェブサイトへの顔写真、氏名、所属、役職の掲載
- 所属機関名およびロゴ画像の本機構ウェブサイト、各種資料への掲載に係る手続きの実行
- 評議員、アドバイザリーボード、協賛企業等への本機構紹介および勧誘
- その他、本機構の広報支援や、エビデンスベーストマーケティングの振興に係る業務
第19条(アカデミックアドバイザーの情報アクセス)
任期中のアカデミックアドバイザーは、以下の規則に基づき本機構の情報を扱う。
本機構の研究成果に関する資料やデータは(総則第4条で定める)秘密情報にあたるため、部外秘(※1)として扱う。委嘱中、または委嘱終了後も、秘密情報の不正な持ち出し(撮影、スクリーンショット取得、コピーを含む)、開示、不正使用は行わない。
※1:本機構内の情報は「研究分科会内でのみ公開」「評議員のみに公開」「評議員、分科会、協賛企業のみに公開」「一般公開」等のレベルにより管理される。管理レベルに沿った情報の管理に努める。
第20条(アカデミックアドバイザーの報酬)
アカデミックアドバイザー就任についての報酬は発生しない。ただし、執筆や登壇など、本機構が定める依頼を受けることで発生する報酬は、個別の取り決めに基づいて支払われるものとする。
第21条(スペシャリスト)
「スペシャリスト」は、本機構の総会(または理事会)が発行する委嘱状で任命されることにより参加できる。また、スペシャリストは、自社が有するサービスやブランドに関するマーケティング活動の一部以上を監督する立場にある者のうち、エビデンスベーストマーケティングに関する知見や実践に取り組む者を対象とする。
第22条(スペシャリストの業務)
任期中のスペシャリストは、原則として以下の事項に取り組むものとする。
- 研究報告会(随時)・大会(年1回予定)への原則参加
- ウェブサイトへの顔写真、氏名、所属、役職の掲載
- 所属機関名およびロゴ画像の本機構ウェブサイト、各種資料への掲載に係る手続きの実行
- 評議員、アドバイザリーボード、協賛企業等への本機構紹介および勧誘
- その他、本機構の広報支援や、エビデンスベーストマーケティングの振興に係る業務
第23条(スペシャリストの情報アクセス)
任期中のスペシャリストは、以下の規則に基づき本機構の情報を扱う。
本機構の研究成果に関する資料やデータは(総則第4条で定める)秘密情報にあたるため、部外秘(※1)として扱う。委嘱中、または委嘱終了後も、秘密情報の不正な持ち出し(撮影、スクリーンショット取得、コピーを含む)、開示、不正使用は行わない。
※1:本機構内の情報は「研究分科会内でのみ公開」「評議員のみに公開」「評議員、分科会、協賛企業のみに公開」「一般公開」等のレベルにより管理される。管理レベルに沿った情報の管理に努める。
第24条(スペシャリストの報酬)
スペシャリスト就任についての報酬は発生しない。ただし、執筆や登壇など、本機構が定める依頼を受けることで発生する報酬は、個別の取り決めに基づいて支払われるものとする。
第5章:会員社に関する規則
第25条(会員社)
「会員社」とは、本機構に所定の会費を支払うことで参加する法人を指す。
第26条(会員社の参加条件)
会員社は、原則として自社で商品・サービスを提供している事業会社が、本機構の定める会費を支払うことで参加することができる。ただし、入会にあたってはエビデンスベーストマーケティングの適用可能性や研究体制を総合的に審査し、大規模データの取得が難しいビジネスモデルや新規性が高く分析手法が確立していない場合、担当する評議員や指導員の不足などによって十分な連携・サポートが期待できないと理事会が判断したときは、参加をお断りすることがある。また、ラグジュアリー系、B2B、BtoBtoB、テック系、政府系、個人事業などを含む特殊な業種・業態であっても、同様の理由で不適当と認められる場合がある。
さらに、これらに当てはまらない場合でも、理事会で協議した結果、本機構の方針や研究活動と合わないと判断されたときは、同様に参加を認めない場合がある。
第27条(会員社のID)
会員社は入会時に、会員社内のメンバーを所定の人数選抜することで、個別にアクセス用のIDを発行できる。IDの数は入会時の申込内容に基づいて決定する。
第28条(会員社が受けられるサービス)
会員社は以下のサービスを受けられる。
- 研究大会(年1回予定)への参加
- ウェブサイトの会員向けコンテンツの閲覧
- エビデンスベーストマーケティング教材の利用
第29条(会員IDの利用規則)
会員ID利用は以下のルールに基づいて利用する。
- 複製不可
- 使いまわし不可(発行対象者以外への共有や第三者への譲渡を禁止する)
そのほか本機構が定めるIDセキュリティポリシーを遵守し、不正利用や不正アクセスの防止に努める
第6章:退会・除名・参加資格の喪失および費用負担
第30条(退会・除名・参加資格の喪失)
本機構の参加者は、「会員社」と「評議員、アカデミックアドバイザー、スペシャリスト、研究パートナー企業」に大別され、それぞれ以下の規定に従う。
- 会員社に関する退会・除名
- 任意退会
会員社は、事務局に対してメールなどの方法で退会の意思を通知することで、いつでも退会できる。退会の意思表示が受理された日をもって退会日とし、以降、本機構のサービスおよび会員特典を利用する一切の権利を失う。なお、すでに納入された会費は退会時期にかかわらず返金しない。 - 会費未納による除名
会員社が会費を未納のまま一定期間を経過しても支払いが確認できない場合、総会(または理事会)は当該会員社を除名できる。未納期間や除名手続きの詳細は事務局が別途定める。除名後、当該会員社は本機構のサービスを利用する一切の権利を失い、発行済みの会員IDは無効化される。 - 重大な規則違反等による除名
会員社が本規則や本機構の名誉・信用を毀損する行為をした場合、総会(または理事会)は当該会員社を即時に除名することができる。除名後、当該会員社は本機構に関する一切の資格や権利を失う。
- 任意退会
- 評議員、アカデミックアドバイザー、スペシャリスト、研究パートナー企業に関する退任・解任
- 任意退任(辞任)
評議員、アカデミックアドバイザー、スペシャリスト、研究パートナー企業(以下「任命参加者」という)は、やむを得ない事情または本人の意向により辞任を希望する場合、事務局に対してメールなどの方法でその旨を届け出るものとする。届出が受理され、総会(または理事会)がこれを承認した時点をもって退任となり、本機構に関する一切の資格や権利を失う。 - 解任
任命参加者が本規則や他の諸規定に違反し、または本機構の名誉・信用を毀損する行為をした場合、総会(または理事会)は当該参加者を即時に解任できる。解任後、当該参加者は本機構に関する一切の資格や権利を失う。 - 任期の継続
任命参加者の任期は、原則として「総会(または理事会)が解除しない限り継続」とする。ただし、本人の辞任申し出、または総会(または理事会)の解任決議によって終了する。
- 任意退任(辞任)
- 共通事項
- 秘密保持義務の存続
会員社、任命参加者を問わず、退会または除名・解任により参加資格を喪失した場合であっても、総則第5条(秘密保持義務)に基づき在籍中に知り得た本機構の秘密情報を開示しない義務は存続する。 - 権利の消滅
退会または除名・解任が確定した時点で、当該参加者の本機構に対するすべての権利は消滅し、本規則に定めるサービスや特典は一切利用できなくなる。
- 秘密保持義務の存続
第31条(会費および研究分科会の費用)
会費および研究分科会にかかる費用については以下のとおりとする。
- 会員社の会費
会員社の会費は年額の固定制とし、基本的には入会時に一括納入するものとする。会員社が追加でメンバーIDを増やす場合などの追加料金やプラン変更の詳細は、別途事務局への連絡により決定する。 - 研究分科会の活動費
研究分科会で発生する調査費用・分析ツール利用料等は、参加企業・参加者の自己負担を原則とする。参加者間で費用負担の調整が必要な場合は、各分科会内で自主的に決定し、本機構は関与しない。
第7章:規約違反・知的財産権および免責事項
第32条(違反時の措置および損害賠償)
規約違反・情報漏洩等が発生した場合の対応については以下のとおりとする。
- 違反時の措置
参加者が本規則に違反し、または本機構の名誉・信用を毀損する行為を行った場合、総会(または理事会)は事実関係を調査し、必要に応じて除名・参加停止その他の措置を取ることができる。 - 損害賠償
参加者の故意または重大な過失により本機構または第三者に損害が生じた場合、総会(または理事会)は当該参加者に対して損害賠償を請求できるものとする。損害賠償の具体的な範囲や金額は、総会(または理事会)の判断により都度決定する。
第33条(知的財産権の取扱い)
知的財産権に関する取扱いは以下のとおりとする。
- 執筆・研究成果の著作権
参加者が本機構の活動の一環で執筆・創作した論文・レポート・プログラム・その他成果物に関する著作権は、原則として執筆者に帰属する。共同研究等で複数の執筆者・研究者が関与した場合、その権利帰属や管理方法は当事者間で別途協議して定めるものとする。 - データ提供者の権利保護
研究分科会等において参加者(企業・個人)が提供するデータの所有権は、提供者に留保される。研究成果の公表・活用に際し、当該データ提供者のノウハウや機密事項が含まれる場合、その公開範囲ついては分科会内または当事者間で協議し決定する。本機構はかかる協議に原則として介入せず、当事者間の合意を尊重する。
第34条(免責事項)
免責事項は以下のとおりとする。
- 研究成果の活用に関する責任
本機構が提供する研究成果や情報は、正確性・有用性などにつき万全を期すものの、それらを利用した結果について本機構は一切の責任を負わない。参加者または第三者が当該研究成果を利用し、損害またはトラブルが生じた場合であっても、本機構は責任を負わない。 - 研究分科会におけるトラブル
研究分科会内での研究活動や共同作業に起因する紛争・問題に関しては、当事者間の協議・解決を原則とし、本機構は責任を負わない。
第8章:規則の改廃および準拠法
第35条(規則の改廃)
規則の改廃に関する手続きは以下のとおりとする。
- 改廃の決定権限
本規則の改廃は、総会(または理事会)において決定する。参加者からの意見聴取は必須ではない。 - 施行時期
総会(または理事会)で改廃が可決された場合、改定版は総会(または理事会)の定める日から直ちに施行されるものとする。
第36条(準拠法および管轄裁判所)
準拠法および管轄裁判所は以下のとおりとする。
- 準拠法
本規則の準拠法は日本法とする。 - 管轄裁判所
本規則に関して紛争が生じた場合、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。